SEOライターで薬機法管理者のななこ(@nnkowriter)です。
私はふだん、在宅でWebライターの仕事をしています。
その仕事内容は、依頼されたテーマやキーワードに対してインターネットで検索をおこない記事にまとめるもの。
自宅にいながらにして、パソコンさえあれば仕事のできるところが魅力です。
そんな私ですが、先日「取材ライティング」の打診を受けました。
リアルな取材をして記事作成をしてもらいたい、とのご依頼だったのです。
リアルな取材をしたことがなかった私ですので、少し悩みましたが「これもライターとしての経験」と思い、お受けすることにしました。
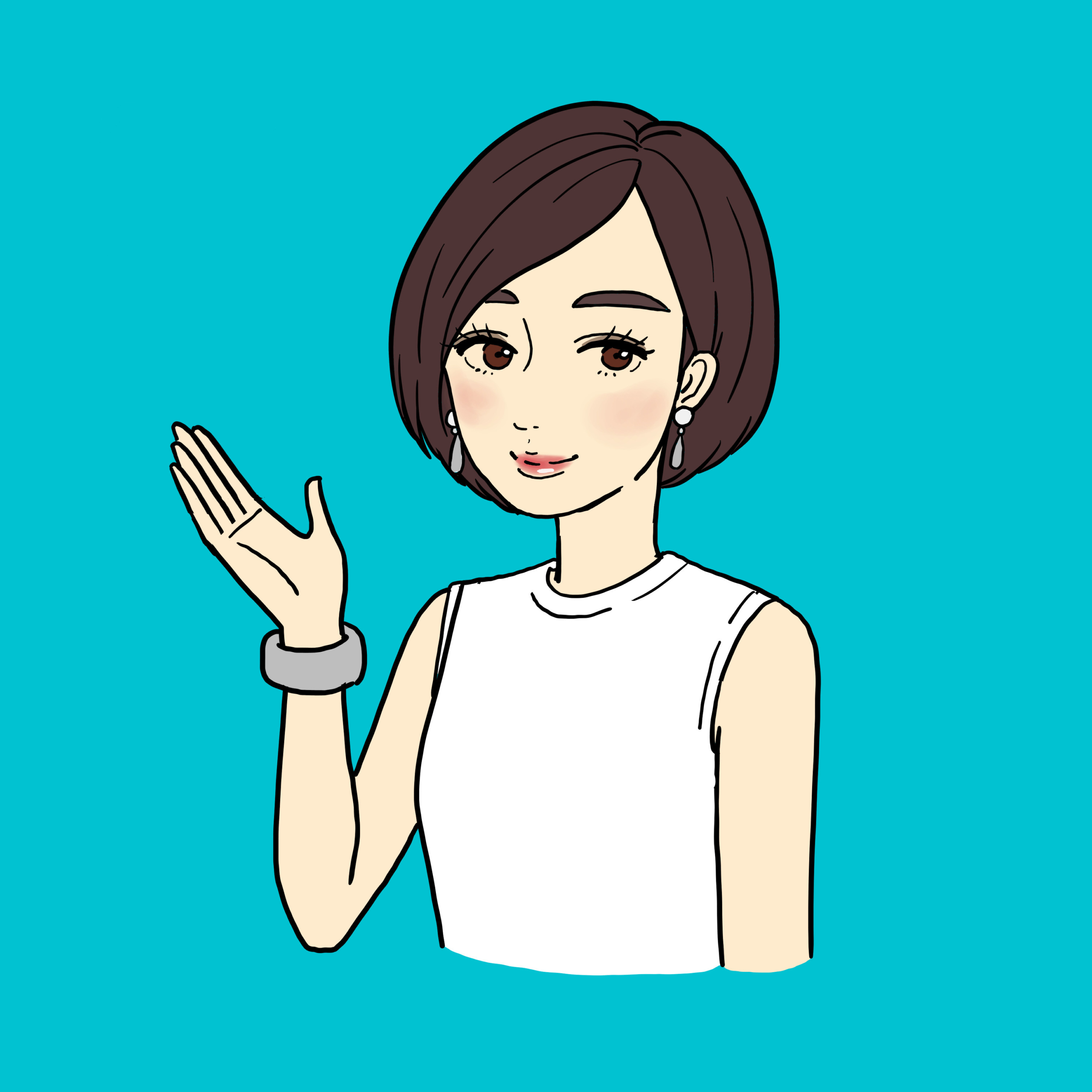 ななこ
ななこ最近、私のまわりでは取材ライターの話題をよく耳にしていたこともあり、興味はあったんですね♪
こちらの記事では、取材ライターについて私の体験をまじえて紹介します。
- SEOライターとして在宅で活動中
- おもにココナラで仕事を受注しています
- ココナラデビュー後約3カ月でプラチナランクを獲得。以降プラチナ継続中
- 現在文字単価4~10円で受注しています
- ココナラ以外でもライター活動受注中
- 多くの方々の添削指導もしてきました
- 毎日ライター活動を楽しく進めています
- Webライターとして活動の幅を広げるために、2021年7月【薬事法管理者】資格取得
- 初心者ライターさん向け『おうちで稼ぎたい主婦のためのWebライター0円講座』は、230名を超える方々に受講していただきました
- ライカレ ものかき大学の『50代からのSEO記事作成講座』にて講師を務める
在宅のWebライターが取材ライターをやるには

ふだん在宅でWebライターとして活動している人が、取材ライターになる方法は簡単です。
取材をともなう案件を受けることですね。
取材の案件を受けるには、以下の方法があります。
- クライアントから依頼を受ける
- 自分で取材ライターの募集を探して応募する
それぞれ説明していきましょう。
取材ライターの依頼を受ける
クライアントから、取材ライターの依頼を受ける方法です。
今回私の場合は、クライアントから「取材をして記事を書いてもらえませんか?」との相談を受けたことがはじまりでした。
それまではずっと在宅でWebライターの仕事をしていた私。
リアルな取材に出向いたことはありませんでした。
普通ならば、「(経験もないので)ちょっと無理です。」とお断りしていたかもしれません。
しかし今回お受けしたのには、いくつか理由があります。
- 以前から、親しいライターさん(ヤンプリさん @yanpuri_writer)が取材ライターをされていた
- まわりのライターさんたちからも「取材ライター」の話題がチラホラと聞かれていた
- ハブ式やその他でも取材ライターさんのセミナーや対談などのお話を聞いていた
そんないくつかの理由が重なり、私には無理だと思っていた未経験の取材案件をお受けしてみようかという気持ちになったのです。
クライアント様には正直に取材経験がないことをお伝えしましたが、「それでもお願いしたい」とまで言っていただいたので、意を決してお受けすることにしました。
在宅でWebライターをしていると、案件は自分で好きなものを選べます。
そのため自分ができそうな案件だけをこなしていくこともいいのですが、新たな分野にチャレンジすることはなかなかできないものです。
たとえば会社で上司から「この案件をやって」と指示をされればやるでしょうが、個人でやっている場合には、誰もそんな指示をしてくれません。
私は、今回取材の依頼をいただいたときに、「やってみれば!?」と天から背中を押されたような気がしたのです。
もちろんライターとして貴重な経験になり、何か次へとつなげられるかもしれないといった思いもありました。
取材ライターの募集をさがして応募する
取材ライターにチャレンジしたいライターさんは、取材ライター募集の案件をさがして応募するのもいいでしょう。
クラウドソーシングや求人サイトで、取材ライターの募集案件を探してみると、かなりの件数がヒットします。
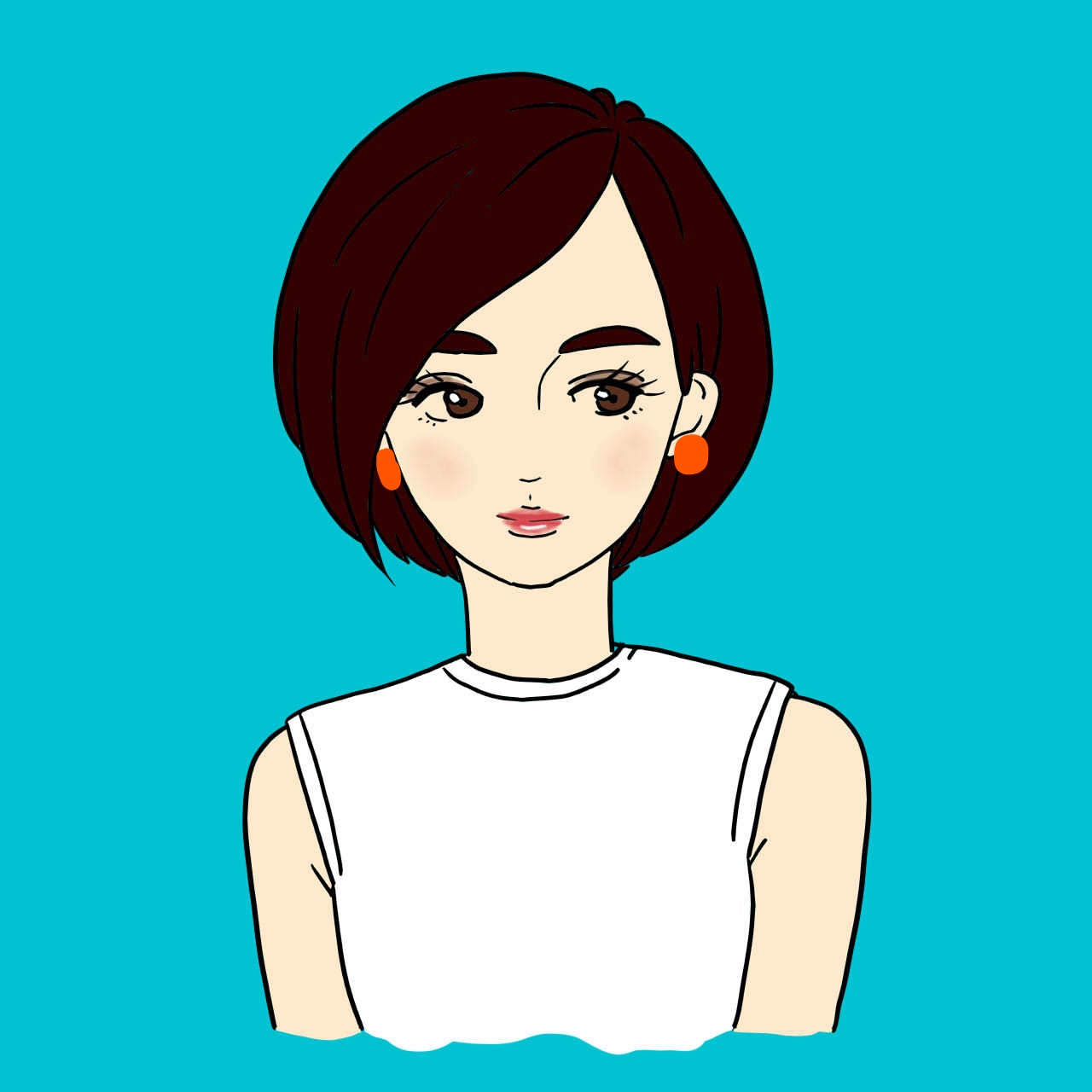 ななこ
ななこ一度、募集の案件をのぞいてみるのもいいですね♪
取材ライターは未経験でもできる?

取材ライターが、未経験でもできるかどうかは、「案件による」といえるでしょう。
今回の私のように、取材が未経験でもOKな場合もあるでしょうし、相当な経験を積んだ人でないと採用にならない案件もあるはずです。
ライターも取材もどちらも未経験だとしたら、いきなり取材ライターをやるのは、かなりハードルが高いかもしれません。
その場合には、まずはライティングの案件を数件こなしてみてライティングのひととおりを身につけて書くことに自信がつけて、それから取材ライターにチャレンジするとよいのではないでしょうか。
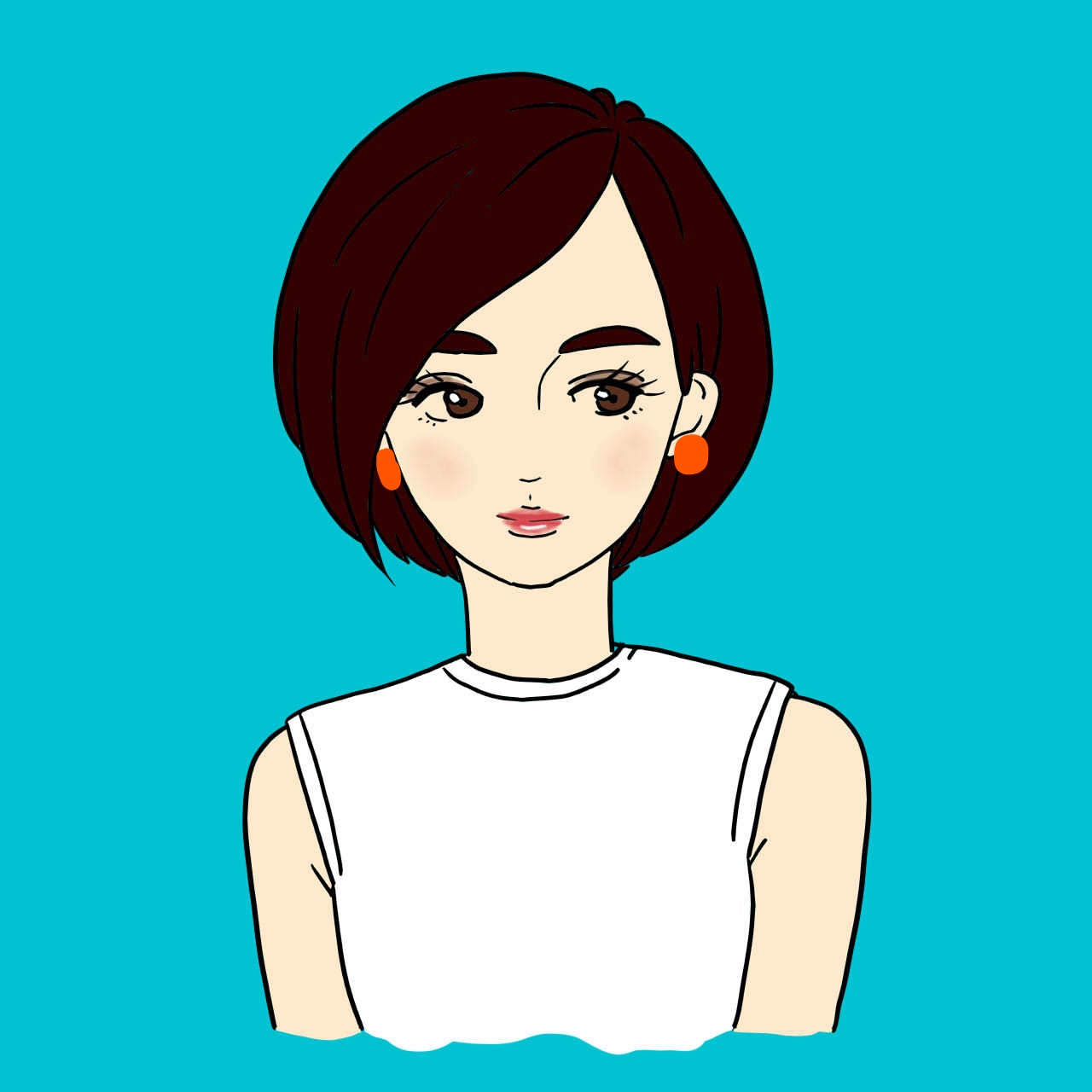 ななこ
ななこ取材は相手があってのことなので、まったくの未経験だと勇気が出ない気がしますね……。
取材ライターの始め方|準備したこと

ここからは取材ライターをするために、私が準備したことを紹介します。
ICレコーダー|ボイスレコーダー(予備の電池や充電など)


取材に行く際に必要だと感じたのが、ボイスレコーダーです。
ICレコーダーとも呼ばれています。
声を録音できるコンパクトな機器です。
今回私が用意したのは、上の画像に写っているオリンパスのICレコーダーです。
あまりにも小さすぎると操作性の面で不安だったので、ある程度の大きさのあるものを選びました。
今回、私の場合は1台でこなしましたが、できれば2台以上の機器を用意するのが安心です。
万が一機器トラブルがあったりうまく声が拾えていなかったりした場合に、1台では取り返しがつきません。
スマホのレコーダーも考えましたが、インタビュー中にスマホの通知が鳴るのが嫌だったので、私は使いませんでした。
また予備の電源は必ず用意しておきましょう。
私の場合は、電池とUSBの両方が使えるICレコーダーなので、予備の電池を用意しました。充電式のものであれば、充電とさらに充電が切れたときの対処法も考えておく必要があります。
なお録音を開始する際には、インタビュイーへこのようにお願いをしました。
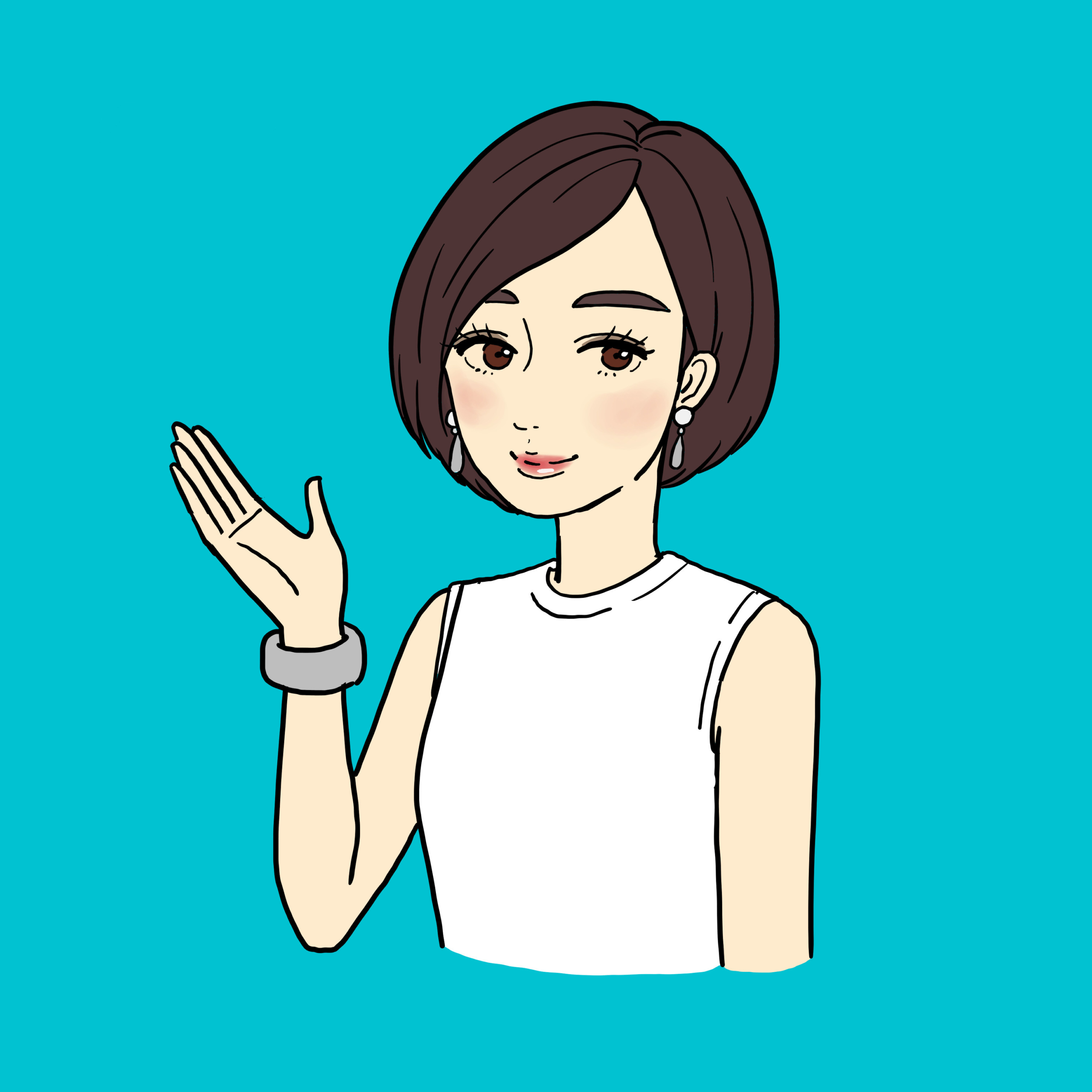 ななこ
ななこいきなり録音をはじめるのは失礼かなと思いましたので、念のためこのようなお声かけをさせていただきました♪
名刺
今回は対面での取材とのことで、やはり名刺は必需品だろうと感じ、名刺をあわてて作成しました。
それまでは在宅でWebライターの仕事をしていたので、名刺の必要性はまったくなかったため持っていなかったからです。
しかしリアルで、ビジネスの場で人と会うということはやはり名刺は必要だと感じました。
名刺の作成については、こちらの記事を参考にしてみてください。
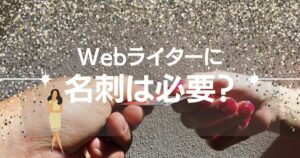
クリップボード

当日は、100円ショップのクリップボードを持参しました。
取材現場の状況がどのような状況かは、現地に行ってみないとわかりません。
テーブルをはさんでインタビューをするのか、立ったままなのか、椅子だけなのか……、そんなことは実際に当日現場へ行ってみないとわからないものです。
どのような状況でもメモが取りやすいように、A4サイズのしっかりとしたクリップボードを持っていきました。
これは以前ダイソーで購入したものです。
テーブルなどがなくても、メモが取りやすいので1つ持っていると何かと重宝しています。
またたとえテーブルがあったとしても、自分にむけて(斜めにして)書けるので、相手から書いた内容が見られないという点では、急いで書くときれいに書けない私にとっては必要な道具でした。
インタビューする質問内容を準備して印刷する
あらかじめインタビューする質問項目をあげ、準備をしました。
インタビュイーについて可能な限りの情報を集め、記事のテーマにあった質問内容を考えます。
質問内容は、取材日以前にインタビュイーにも目を通してもらっておくと安心です。
質問項目は、A4用紙に3~4つくらいの質問が載るように印刷し、前述のクリップボードへはさんでいきました。
なおノートパソコンやスマホでの入力が得意な方は、紙にメモではなくノートパソコンやスマホにメモでもいいでしょう。
私の場合は、入力に自信がないので紙を選びました。
また紙であれば、取材中に話が前後したりしても、さかのぼった項目にメモすることが自由自在なので、かなりよかったです。
カメラは状況に応じて準備する
今回は、写真はカメラマンさんが撮るとのことだったので、私がカメラを用意する必要はありませんでした。
しかし、写真撮影もライターがおこなう案件もよくあるようです。
写真の撮影も依頼に入っている場合には、カメラなどの機材も必要となります。
スマホの撮影でも大丈夫なのか、それなりのカメラが必要なのか、そのあたりの条件も事前に確認しなければなりません。
Webライターと取材ライター| 仕事内容の違い

ここからは、Webライターと取材ライターの、仕事内容の違いをまとめてみます。
- Webライターは検索して記事を書く
- 取材ライターは取材して記事を書く
それぞれ説明しましょう。
Webライターは検索して記事を書く
Webライターは、依頼のテーマやキーワードに対して、ネットで検索をおこない記事を書いていきます。
ネットでリサーチをおこなったら、構成を作成し、その構成に本文を執筆していくのです。
記事作成のためには、ネットの検索は欠かせない作業となります。
また私のようにSEOライターとして記事作成をおこなう場合には、記事作成に加えてSEOに強い施策が必要です。
取材ライターは取材して記事を書く
取材ライターは、取材をし、その内容を記事へまとめます。
そのためネットで検索は不要かとも思われそうですが、私の場合は取材のデータをもとに、やはりネットで検索をして裏取りをしながら執筆するといった作業をしました。
また取材準備の段階でも予備知識を入れるために、インタビュイーやその方の職業などについて、かなりのネット検索をする必要がありました。
さらに記事作成の段階でも、検索作業は必要です。
私はSEOライターとして、作成した記事をより上位に検索されるようにさまざまな施策をとり記事作成をおこなっています。
今回の取材記事も、可能なかぎり上位に表示させたいために、必要なSEOのリサーチや施策はでき得るかぎりおこないました。
取材の仕方

ここからは、取材の仕方を紹介しておきましょう。
ひとことで「取材」といっても、じつにさまざまな方法があります。
私はこれまで取材を受ける側(インタビュイー)の方が多かったので、私が実際に受けた取材の形についても紹介していきます。
- リアルな取材
- zoomなどを活用したオンラインの取材
- メールやフォームなどで質問項目を準備して答えてもらう
- 電話で取材する
リアルな取材
いわゆる「取材」といってイメージするのが、リアルな取材です。
- インタビューする相手にあって話を聞く
- 店舗や施設へ行って取材する
私が取材を受けた側の経験としては、以前テレビの取材を受けたのですが、そのときはまさにリアルな形での取材でした。
プロデューサーさんと、カメラさん、音声さんとそろって取材に来てくださり、取材を受けたのです。
プロデューサーさんは、やはりさすがプロ。
さり気なくカメラマンさんが撮影を進めている最中にも、自然とこちらへ質問を投げかけてくださり、後から思うとあれもすべてインタビューだったんだ、と感じました。
そのときの体験記事はこちらから。
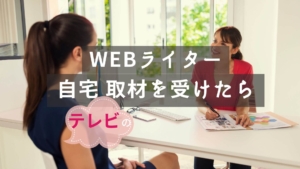
zoomなどを活用したオンラインの取材
コロナ禍となり、これまではリアルな取材があたりまえだったケースも、オンラインでの取材へと移行しているものも多いようです。
zoomなどを活用すれば、まるで対面で話を聞くのと同じようなイメージでインタビューができます。
私は先日、ライターのお仲間であるはなさん(@hana_writer_)から、オンラインで取材をしていただきました。
このときに感じたのは、はなさんがとてもやさしい雰囲気で私の話を聞き出してくださったこと。
また私が話したことに対して、的確に温かみのある反応を示してくださったのです。
このことから私はとても話しやすく、楽しんでインタビューの時間を過ごせました。
今後インタビューをする立場になったら、私もはなさんのように相手が話しやすい環境づくりを心がけようと思いました。
そのときの、はなさんが書かれたnote記事はこちらです。
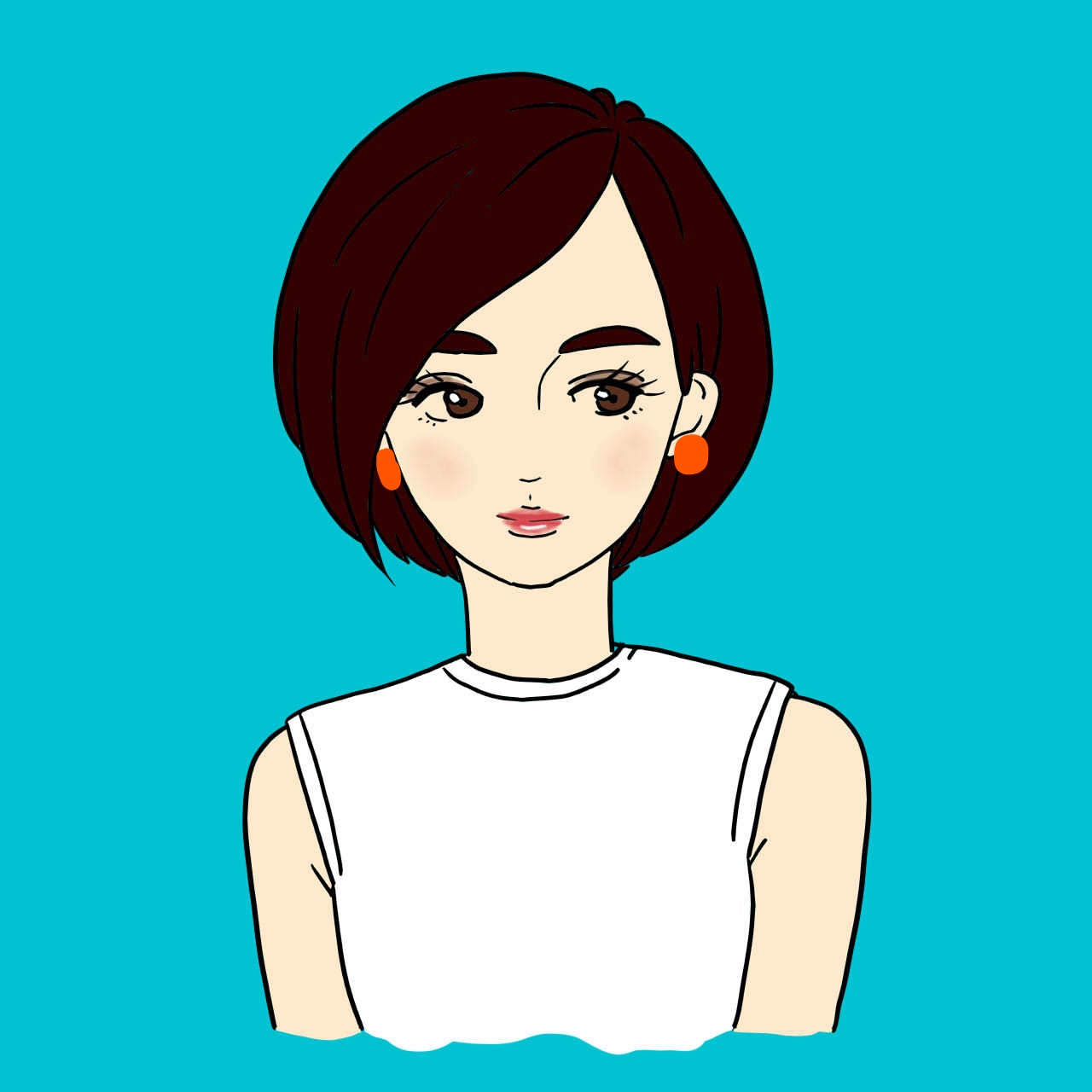 ななこ
ななこ取材記事としてのまとめ方も、とても参考になりますよ♪
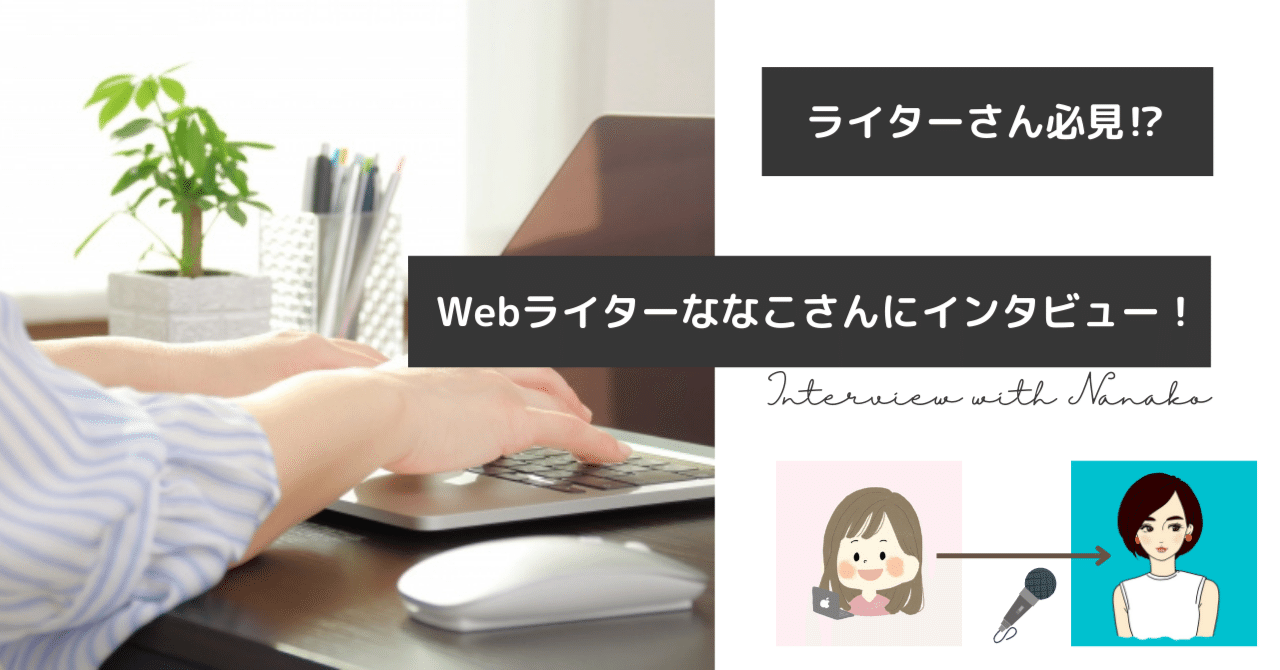
メールやフォームなどで質問項目を準備して答えてもらう
会話形式ではなく、メールやGoogleフォームなどに質問事項を準備して、それに対してテキストで答えてもらう、といった取材方法もあります。
インタビューを受ける側は、じっくりと答えを考えられるので、話すことがあまり得意でない人も答えやすいでしょう。
ただしあくまでも文章になるので、「生の声」としてはやや面白みに欠けるかもしれません。
私は、以前電子書籍の取材やココナラマガジンの取材をこの形式で受けたことがあります。
そのときの電子書籍はこちら。

50歳からのライターの教科書 ライター1年目の教科書 (ものかき出版)
ココナラマガジンの監修記事はこちら。
電話で取材する
電話でインタビューする取材形式もあります。
テキストでの取材よりも、zoomやリアルの取材に近い感じですね。
双方向の会話で進むため、やりとりの中から引き出せる要素があるかもしれません。
私は以前、テレビの取材を受ける前段階の取材は、この電話取材といった形で取材を受けました。
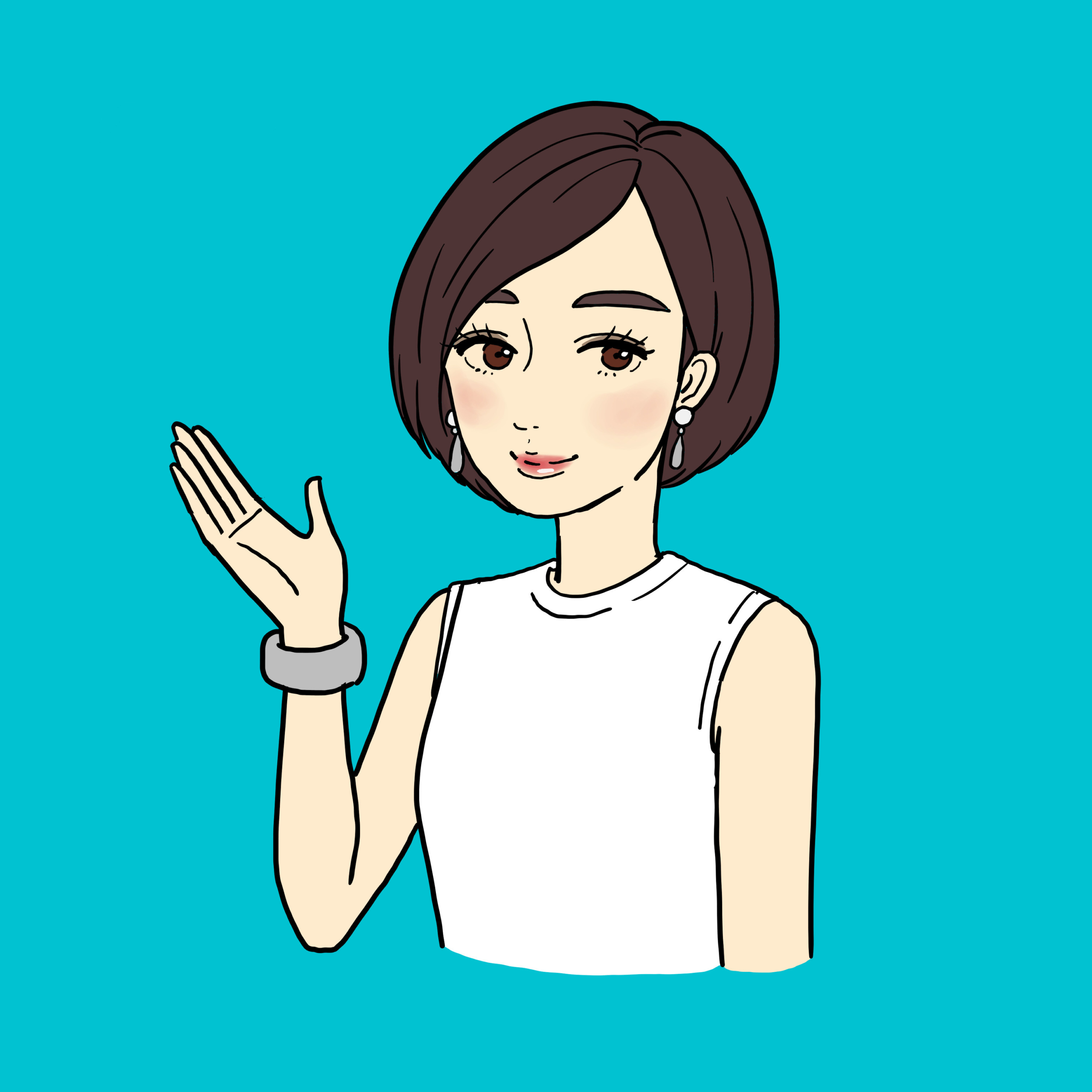 ななこ
ななこそれぞれメリットやデメリットがあります。取材が未経験のライターさんにとっては、テキストでの取材が一番難易度が低いかもしれませんね♪
インタビュー記事を書く手順

取材が終わってから記事を書く手順を紹介します。
インタビューが終わったらなるべく早くに書く
インタビューが終わったら、なるべく早くに書くのがいいでしょう。
人間の記憶はどんどん薄れてしまうからです。
まずは音声データを聞きながら、それを文字起こししていきます。
いきなり書かずに内容や流れをまとめて構成を考える
文字起こしがすんだら、内容や流れをまとめて、記事の構成を考えます。
意外と質問や回答が前後している部分もあったり、重複している内容もあったりするので、そのあたりも整理しながら進めなければなりません。
適宜質問を見出しに設定するなどして、SEO的にも有利になるように考えます。
記事作成をする
構成がかたまったら、執筆をしていきます。
執筆は普通の記事よりも、スムーズに進むでしょう。
なぜなら、執筆の段階ではもうすでに書くことが確立しているからです。
推敲してWordPressへ入稿する
文章がかけたたら推敲し、WordPressへ入稿します。
適宜画像を設定し、文字装飾などで読みやすく仕上げればインタビュー記事の完成です。
取材ライターの相場は高い?

私はふだんSEOライターとして記事作成をおこなっていますが、それに比べると取材ライターの記事作成の相場は高いといえるでしょう。
今回文字単価で計算すると、1文字10円以上ではありました。
しかし取材ライティングの場合には、事前の準備や取材先まで出向く労力と拘束時間、その後文字起こしをして構成をたて記事に仕上げるまでの一連を考えると、妥当といえば妥当かもしれません。
往復の交通費や、宿泊をともなうのかどうかなど、諸条件も事前に確認する必要があります。
取材ライターを経験してみて

今回取材ライターを経験してみての感想は、「とても楽しかった」ということです。
在宅で仕事をするのとはまったく違って緊張感がありましたが、やはり人と対面で仕事をするのはこんなにワクワクするものなんだと、感じました。
私がWebライターをはじめてからまもなくコロナ禍となってしまったため、在宅で仕事をすることや、なんでもオンラインでおこなうことがあたり前の時代に。
私にとっては、在宅で仕事ができることは「最高」だと感じていましたが、リアルで人とお会いして仕事をすることはまったく別の楽しさがありました。
今では、また機会があればぜひ取材にでかけてみたいと思っています。
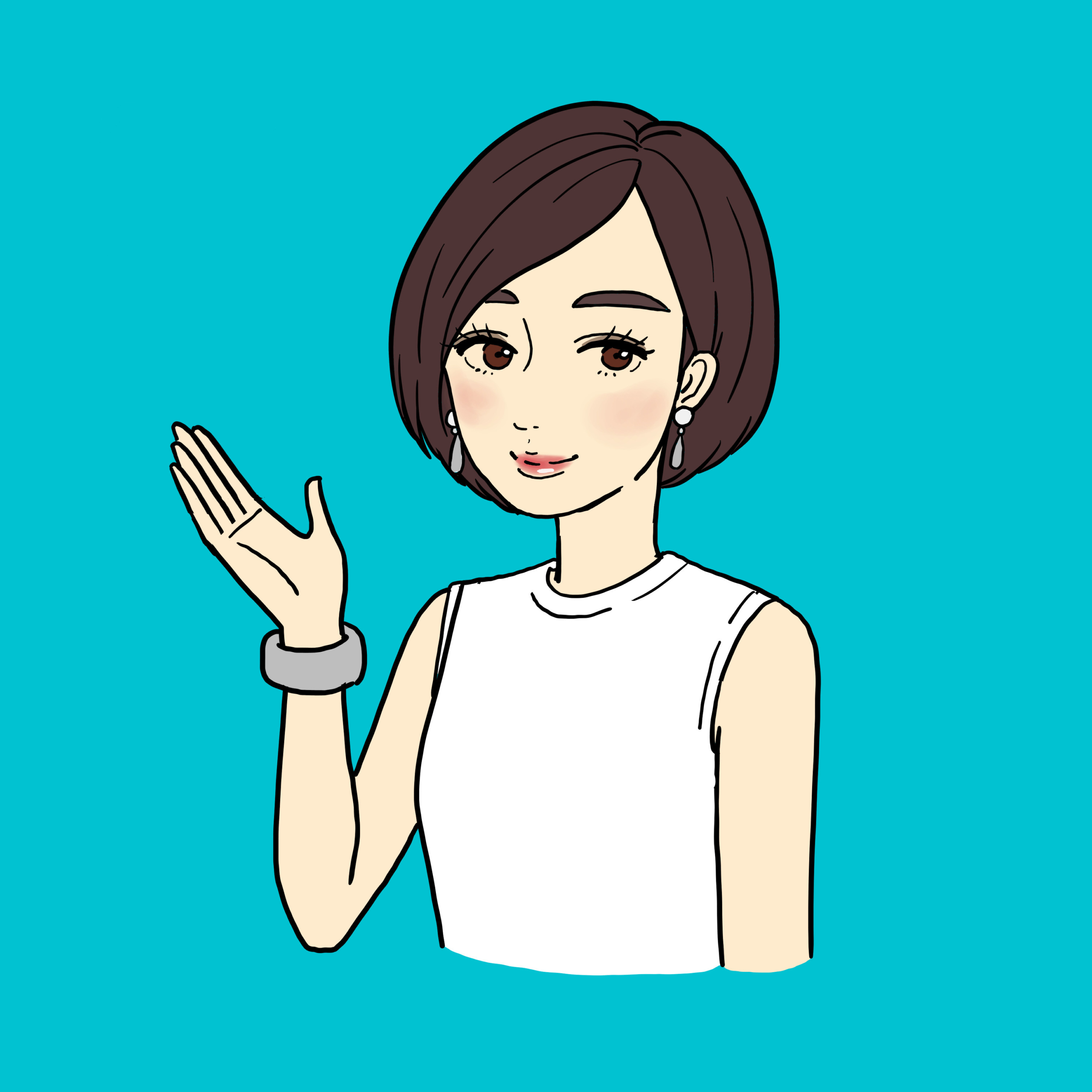 ななこ
ななこやはり実際に人と会ってお仕事ができたことは、本当に楽しかったですね♪
Webライターと取材ライターはどちらも文章を書く仕事!活動の幅が広がる

在宅のWebライターとして活動してきた私は、これまで「取材ライター」のお話を聞いても、どこか「私には無理」「私にはできないな」と思っていました。
そのため、今まではあえて自分からチャレンジしようとは思わなかったのです。
今回お声かけをいただきチャレンジしてみて感じたことは、Webライターも取材ライターも、どちらも文章を書く仕事。
「取材ライターもできます。」といえるライターさんの方が、今後活動の範囲も広がるのは確実です。
もしもチャンスがあったら、思い切ってチャレンジしてみてはいかがですか。
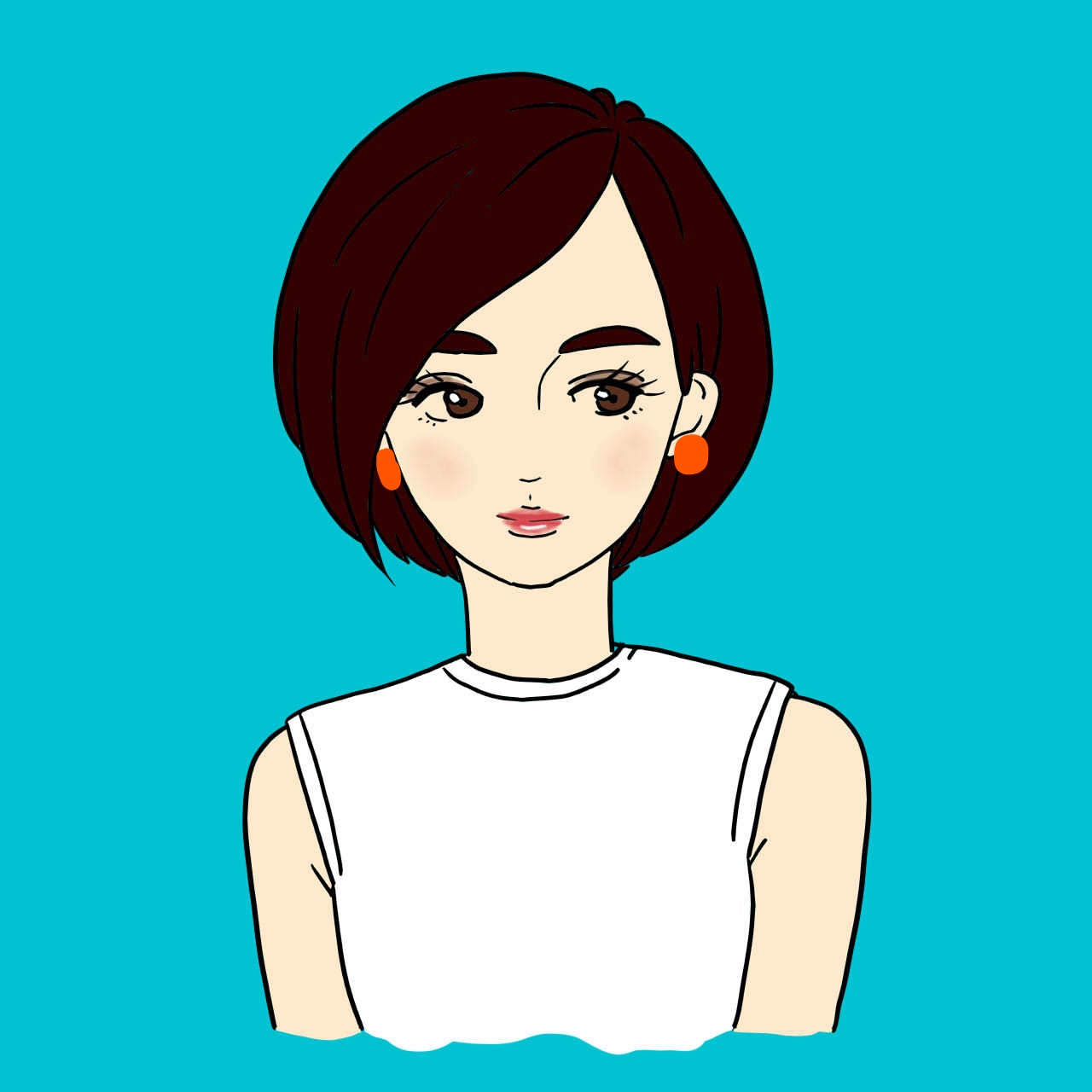 ななこ
ななこ取材ができるライターさんはまだまだ多くないそうです♪ 実際に体験してみて、人の話を聞くのが好きな方にとても向いていると感じました。

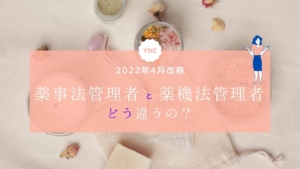





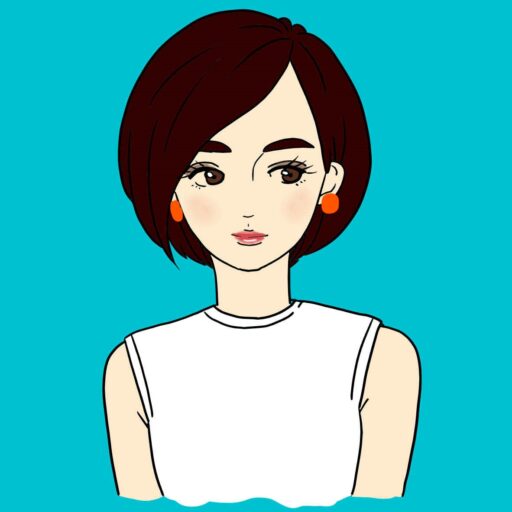
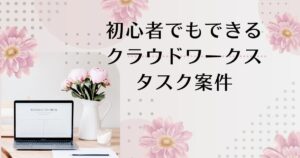
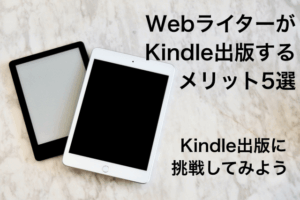

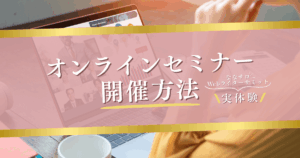
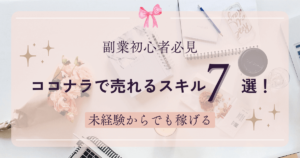
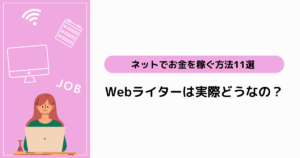
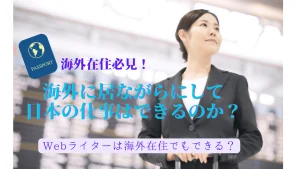
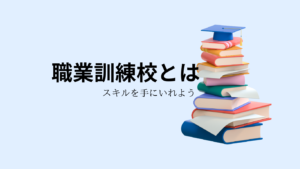
コメント